小学生になると宿題や予習、復習など勉強に取り組む時間が必要になります。
小学校へ入学したタイミングで、子供部屋での学習、リビング学習をすることになりますが、学年によって集中できる時間は異なります。
お子様が集中できる時間を知ることで適切な声がけや配慮ができるので、子供の勉強時間の目安を把握しておくことをおすすめします。
今回は、子供の勉強時間の目安やおすすめの教材などについてご紹介します。
子供の勉強時間の目安
子供の勉強時間の目安は、一般的に学年×15分と言われています。
まずは、子供の勉強時間を年齢別でご紹介します。
子供の勉強時間の目安・小学1年生から2年生の場合
子供の勉強時間の目安は、小学校1年生の場合 1(学年)×15分=15分と言われています。
低学年の場合は、15分から30分程度が勉強時間の目安になります。
小学校へ入学したばかりの頃は、勉強する習慣がついていないので、なかなか集中できないこともあるでしょう。
しかし、勉強する習慣は、毎日行うことで自然に身につきます。
学校から帰宅したらすぐに遊びではなく、勉強という流れが習慣になるように、お子様が帰ってからすぐに勉強ができる環境に整えておきましょう。
環境を整えることがポイント!

例えば、お子様が帰ってすぐにゲームやおもちゃなどに目が行くと、勉強する気持ちがなくなる可能性があります。
帰宅し、手洗いうがいを済ませたら子供部屋、リビングなどで勉強することがルーティーンになれば、効率的な学習へ繋がります。
お子様は、帰宅したら勉強モードに入りやすくなるので、勉強が終わったら○○するという流れを作ることもおすすめです。
- 勉強が終わったらおやつ
- 勉強が終わったらゲーム
- 勉強が終わったらごはん
ゲームのようにお子様にとって楽しみがあれば、勉強へのやる気にも繋がるでしょう。
子供の勉強時間の目安・小学3年生から4年生の場合
子供の勉強時間の目安は、小学3年生から4年生になると45分以上から1時間程度です。
低学年より長くなります。
学習量が増えることで宿題も増えますが、集中力も身についているので、宿題と予習・復習などにも取り組むことができるでしょう。
子供の勉強時間の目安・小学5年生から6年生の場合
子供の勉強時間の目安は、高学年になると更に長く取り組むことができるようになります。
大体1時間15分から1時間半ですが、中学受験をお考えであれば、更に受験対策も必要になります。
土日の子供の勉強時間の目安は1時間程度
子供が勉強に取り組む時間は、平日だけではなく、土日も作ることをおすすめします。
先程ご紹介した通り、勉強は毎日行うことで習慣になります。
休日でも1時間程度を目安にして行いましょう。
特に、朝は記憶力が高まり、やる気も出やすい時間と言われています。
翌日が休日の場合は、夜更かしするお子様もいるようですが、普段通りに起床して勉強に取り組み、その後で外出、ゲームなどの楽しみを設けることをおすすめします。
休日でも勉強することで、毎日取り組むことが、お子様にって当たり前のことになるでしょう。
子供の勉強におすすめの教材【すらら】とは
【すらら】は、アニメーションキャラクターが先生役で、楽しく学べる、無学年式オンライン教育サービスです。

すららは、小学生、中学生、高校生向けのオンライン教育サービスで、インターネットをつないでご家庭のパソコン、タブレットなどで学ぶことができます。
すららは、国語、数学、理科、社会、英語の5教科に対応しており、先生役のアニメーションキャラクターと一緒に、お子様の理解度に合わせて楽しく学習できます。
すららの魅力

すららには、ゲーミフィケーションという飽きさせず、ワクワクさせる機能があります。
学習量をクリアするミッションがあり、達成するとポイント付与、アバターの変更、パートナーの育成、着せ替えなどもできます。
ゲーム感覚で勉強することは、子どもの記憶に残りやすく、楽しく集中して勉強に取り組む効果も期待できます。
不登校に対応!
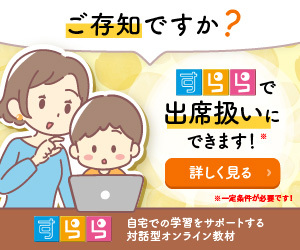
すららの「見る・聞く・書く・読む・話す」という色々な感覚を使う学習法は、発達障がい、不登校
のお子様の個性や様々な要望にも対応しています。
無学年式のオンライン教材を使用しており、全国300人以上の不登校のお子様が出席扱いとして認められているという実績もあります。
無料体験実施中!
すららでは、無料体験を実施しています。
89.1%のお子様がすららを継続しており、サポート体制も充実していますから、是非この機会に無料体験へ参加してみませんか。
まとめ
子供の勉強時間の目安についてご紹介しました。
子供の年齢によって勉強時間が異なることがお分かりいただけたでしょう。
家庭での勉強は、学校の宿題だけではなく、学習教材の利用もおすすめです。
お子様が好きなキャラクターやアニメーションであれば、楽しく学習に取り組むことができますので、長く、続けることができる教材を選びましょう。




